コロナ禍によりテレワーク化が進んだことで、さらに踏み込んだ成果主義を導入したいと考える企業が増えています。しかし、この成果主義によい印象を持っていない人も多いのではないでしょうか。「協調性を重んじる日本企業にはなじまない」という意見には納得感があります。実際、かつて日本では成果主義が脚光を浴び、次々と企業に導入された時期がありました。しかし、それにより「社員の意欲が高まった」「業績が回復した」という企業は多くありません。なぜ、日本企業では成果主義がうまくいかないのか――。過去の失敗事例を紐解きながら、効果的に機能させる方法を考えます。
成果主義とは?
まず、成果主義の定義から振り返りましょう。成果主義とは、個人の仕事を成果に応じて評価し、対価や処遇を決める考え方のことです。海外から輸入された言葉で、もともとの英語に戻すと「Result-based Human Resource Management」。つまり、結果に基づいて人材の管理を行うことだといえます。
明確な対義語ではないものの対局にある考え方が、成果ではなく勤続年数や年齢で評価する年功序列。あるいは、労働時間の長短だけで対価を決定する時給制。さらには、生活補助色の強い住宅手当・家族手当といった待遇も、仕事の成果と紐づくものではないので成果主義の対局にあるといえます。成果主義とは、こうした仕事の成果以外で評価することを極力排除し、企業の業績に貢献する成果を高く評価しようとする仕組みのことです。
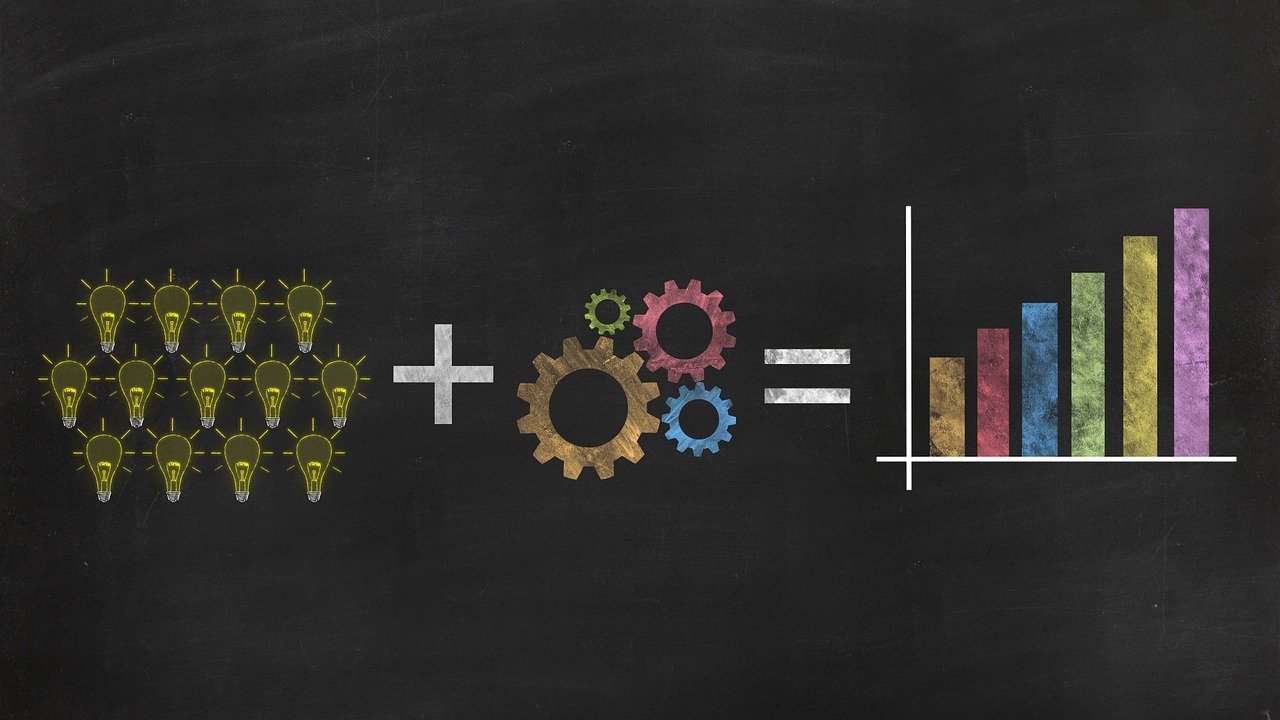
ここで気になるのが、「成果とは何か?」ではないでしょうか。企業によって捉え方に多少の差はあるものの、「成果主義における成果」とは、一般的には業績に貢献した何らかの結果のことをいいます。実際の運用に置いた場合は、立てた目標に対する達成状況です。
たとえば、「月間の売上500万円必達」と目標設定を行った営業メンバーがいたとします。「売上500万円以上」であれば「成果あり」になりますし、残念ながら未達なら「成果なし」になります。目標は個人が設定する場合もありますし、会社が設定する場合もあります。それは、企業によってさまざまです。
先述の通り、成果主義はアメリカから輸入されたものです。輸入時期は、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、つまりバブル崩壊後でした。経済が極端に低迷する中で、社員のモチベーションを高めるための「カンフル剤」として導入されましたが、結果は惨憺たるもの。従来の日本の雇用慣行に成果主義がそぐわず、数年のトライアルをへて、大幅な軌道修正をした企業が続出しました。以下で、実際の事例をもとに残念な末路をたどった成果主義の敗因を探ります。
事例から学ぶ、成果主義の「敗因」と、そこから得られる「気づき」
(1)目標をあえて低く設定する人が続出、業績向上にはならず
成果主義における成果とは、目標に対する達成状況であることから、目標設定が起点にあります。先に述べた通り、目標を上回れば高い評価となり、下回れば低い評価となります。このことから、「低い目標を設定したほうが得だ」と考える人が続出したといいます。
たとえば、「自分には、現時点において売上を月間500万円あげられるポテンシャルがある」と見積もったとします。目標を400万円に設定すれば「高評価」を得られるし、目標を600万円に設定すると「低評価」になる。であれば、低めに設定した方が得だと考えるのが人の常。結果として、大多数の人が容易にこえられる手堅い目標しか立てなくなり、当初の狙いにあった業績向上にはつながらなかったとのことです。もちろん、個人レベルでのスキル向上にもつながりませんでした。
(2)自己保身に走る人が増え、チームワークが機能しなくなる
成果主義の導入により、分かりやすい「個人の成果」ばかりが評価されるようになった結果、チームワークが機能不全に陥りました。ハイパフォーマーがチームメンバーに自分の持っているノウハウやネットワークを提供しなくなったり、業務が誰かに偏ったときに、サポートしなくなったりしたのです。
誰かの仕事を手伝ったところで、成果主義のもとでは自分の評価にはつながりません。「あの時、俺が手伝ってやったから、あの大きな案件を受注できたんだ」とアピールしたとしても、やはりそれは他人の成果であり、自分の成果としては認められづらいからです。結果として、人間関係が次第にギスギスとしていき、知識やノウハウ、人脈の伝承も途絶えました。最大の弊害が、若手が育たなくなったことだといいます。これは三井物産や日本マクドナルドの事例をもとにした、成果主義の敗因です。

(3)管理するメンバーの数が多すぎて、目標・成果管理が行き届かない
成果主義においては、目標の設定が起点にあり、成果の評価が終点にあるといえます。これらの管理は各部門のマネージャー(部長など)が担うことが多いですが、大きな組織のマネージャーともなると、配下に100名くらいのメンバーがいます。その一人ひとりの立てた目標を、仕事ぶりと照らし合わせながら丁寧に評価ができるか。否、そう簡単なことではありません。
過去に成果主義を導入した富士通では、評価を担う部長も人事部も、山積みにされた目標管理シートに目を通すことすらなかったといいます。「見てもよく分からないんだよね」という人さえいたそうです。結果として、目標管理は有名無実化したそうです。
(4)長期で取り組むプロジェクトが、評価されづらくなる
6カ月程度の期間で評価が決まるとなると、どうしても損をするのは長期プロジェクトに取り組む人たちです。企業の中には、短期で成果を出せない種類の仕事に取り組む人もいます。たとえば、日本の大手メーカーには中央研究所と呼ばれる研究開発拠点があって、そこでは日々、終わりの見えない研究がなされています。必ずしもすぐに売上に直結しなくても、将来的に有用となるであろう基礎的な研究に取り組んでいるのです。
このような先の見えないプロジェクトに取り組む人たちが、評価されずに不満を抱え始めると、企業から新しい技術や事業が生まれづらくなります。そうすると、企業として競争力も衰えていくことになります。
(5)成果の定義づけが難しい職種のモチベーションが低下する
企業の中には、利益を生み出す職種と、利益を生み出さない職種があります。前者の代表は営業などのフロント職。後者の代表は人事・総務・経理などのバックオフィス職です。フロント職は、成果主義においてもっとも陽の目を見やすい職種です。シンプルに成果(売上)をあげればあげるほど、高い評価につながるからです。一方で、バックオフィス職は成果の定義づけが難しく、うまく機能させることが困難だといえます。チームでひとつの業務に取り組んでいる場合は、なおさらです。
実際に富士通では成果主義導入後、製品の最終チェックを担う品質管理部門のモチベーションが著しく低下し、不良品が数多く世に出回ったといいます。それが、企業全体のブランドを毀損する結果ともなったそうです。
(6)社内での戦いに疲れた人が、社外活動に精を出し始める
どんな組織でも、「優秀な人(ハイパフォーマー)2割」「普通の人(一般的な業務遂行能力を有している人)6割」「目標の成果を出せない人(ローパフォーマー)2割」へと自然と分かれていくという法則があります。「2-6-2の法則」と呼ばれるものです。成果主義が適切に機能すれば、高い評価を得るのは、上位の2割になります。この2割は評価期間毎に入れ替わる可能性もありますが、人の入れ替わりが少ない組織では固定化しがちです。
上位2割に入れない人たちが、どうなったのか。「高評価なんていらないし、競争にさらされて疲弊するくらいなら、出世しなくてもいい」と考えるようになったといいます。その人たちは、黙々とルーティンワークに精を出すようになりました。中には、会社以外の活動に生きがいを求めはじめた人もいるそうです。

「成果主義」の成否を分ける2つのポイント
これらの失敗事例から見えてくる、成果主義をうまく機能させる重要なポイントとは何でしょうか。2つあるのではないかと思います。
一つ目は、「成果の定義づけ」です。チームワークで成り立つ種類の仕事や、バックオフィス関連、さきほどの品質管理部門など、業績に紐づいた成果の定義づけが難しい職種の成果を何と定義するか。ここがひとつ重要なポイントです。
二つ目は、「成果管理者の資質」です。目標管理・成果管理は、時間管理よりも遥かに難しい仕事であることは言うまでもありません。バブル崩壊直後に、日本企業が成果主義をこぞって導入した際には、成果の管理者に経験も知見もなかったことから、適切な目標管理、成果管理ができなかったのではないかと思います。年功序列制度の中で、年齢・勤続年数だけで立場の上がった人に、適切な成果の管理ができたのかは疑問です。
ですから、誰に成果の管理者を担ってもらうか。この人選には、細心の注意を払う必要があります。一つ目の「成果の定義づけ」も、結局のところ成果の管理者が担うことになるでしょう。成果の管理者として、成果を出せる人を確保すること。これが、成果主義をうまく機能させるための第一歩であり、最大のポイントなのではないでしょうか。

まとめ
成果主義を導入する場合、従来の時間管理型を残して、成果主義を上乗せするのか。あるいは、時間管理型を撤廃して裁量労働制にしたうえで、完全な成果主義に切り替えるのか。方法は2つあります。
すでに前者の「時間管理型・成果主義」になっている企業はたくさんあります。少なくとも大企業のほとんどは、目標管理を導入済です。コロナ禍によるテレワーク化で起こりうる変化は、時間の管理が難しいため、後者の「脱時間管理型・成果主義」へとシフトすることです。
いずれにせよ、重要なポイントは同じでしょう。「成果の定義づけ」と「成果管理者の資質」が成否を分けると思います。とくに、成果の定義づけが難しい部門の成果管理者は、巧みな手さばきが求められるはずです。繰り返しになりますが、この人選が肝です。
最後にひとつだけ。下記の参考書籍の中で、とても印象深かった部分があります。著者の城氏が「生身の人間に対する考察」が完全に欠如していたと振り返る部分です。新たな評価制度はシステマチックに導入すれば機能するものではありません。人間は機械ではないからです。生身の人間を考察しながら、大胆かつ慎重に進めていくことが大事だと思います。

大学卒業後、人材サービス大手で約12年間勤務。主に企業の採用活動に携わる。採用という入口だけではなく、その後の働き方にも領域を広げたいとの思いで独立。現在、採用支援を手がける傍ら、働き方に関するコンテンツなども執筆しています。京都大学文学部卒業(社会学専攻)。2015年、社会保険労務士の資格取得。














